俊六と猫と二人のをんな -1-
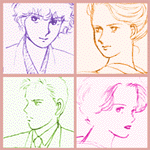
昭和二十四年。
おちかはおせつが好きだったので、どうにか風間の正妻におせつを据えたいという野望を持っていた。葉山千賀子、三十二才、一世一代の陰謀である。
「先生、ちょっと」
風呂から上がって髪を拭きながら松月の廊下を歩いていた金田一耕助はおちかに呼び止められて立ち止まった。
「やあ、おちかさん、何か?」
「ちょっとこっちへ」
おちかは耕助を使っていない客間へ招いた。
「先生、あなた恩知らずじゃないこと?」
薄暗がりで、下から見上げるおちかのきらりと光る射るような瞳に押されて、耕助の表情も険しくなった。
耕助は男としては小柄で貧弱な方だが、女のおちかは当然もっと小さい。というより、おちかも女性の中でも小柄な方だった。しかし、耕助と違って、少しつり上がった大きな丸い目や、溌剌とした感じが、山椒は小粒でもぴりりと辛い、といった雰囲気の女であった。
「……」
黙っていると、おちかが再び口を開いた。
「私の陰謀に一口乗って欲しいの」
「陰謀ぅ?」
「旦那の奥さんに、おかみさんを据えたいのよ。お世話になってんのに、何とも思わないの?先生になら旦那も頭が上がらないし、どうにか言ってやって欲しいんだけど」
おちかは相変わらず厳しい顔で耕助を見上げていたが、耕助は顔の緊張をゆるめ、笑うと、
「なあーんだ。それはぼくも賛成だ。でも、ぼくもずっと説教してるが、馬の耳に念仏だぜ」
「だからちょっと工作しようと思ってんの。協力してくれるわよね」
「そりゃいい。日頃お世話になってるお礼だ」
二人がこそこそと薄暗がりで協議して出てきたのは、二十分後であった。
おちかは母屋の方へ、耕助は離れへと消えていった。
「風間、近頃の調子はどうだい?」
翌日、耕助は風間俊六の事務所へと足を運んだ。風間はお茶を持ってこさせると、ソファに向かい合って座った。風間は、いつもよれよれの袴姿の耕助と違って、社長らしく、颯爽とスーツを着ている。
「どうしたんだい?金でも足りなくなったのか?」
風間は笑いかけた。
「嫌だな。おれがそんないやしい男と思ってるのかよ。ただ単に遊びに来ちゃ、いけない?」
耕助はちょっとふくれて見せた。
「そんな事いったって、君は現金で無精だからな。下心なしでわざわざこんな所まで来る奴じゃない」
――うっ、見抜かれてる(当たり前だ…)
「耳が痛いね…ねえ、今日ヒマかい?」
「んー…?まあ、ヒマではないが、忙しい訳でもない」
「じゃあ今日、帰りに、…」
と金田一耕助が言いかけると、風間は弾かれたように立ち上がった。それで耕助は驚いて、そのまま言葉を失い、風間を見ていると、風間は自分のデスクの引き出しから茶封筒を取り出し、また座った。
「な…風間、その封筒が、何か…?」
探るように耕助が言うと、風間は封筒を開けながら、…突然ぱあっと晴れやかに笑った。
「うん、東劇のキップ、貰ってたんだ。今日までなんだ、耕ちゃん、行こうぜ」
「えっ、今から?…待って、おせつさん呼ぶから、」
耕助は願ってもないチャンスと思った。
立ち上がってデスクの上の電話に手を伸ばそうとすると、その手首を風間が掴んだ。
「いいよ、耕ちゃんと見に行きたいから」
そのまま風間はUターンすると、腕を掴んだまま片手でバッグを取り、引きずって社長室を出ていった。
「ちょ、ちょっと、待ってくれよ、おせつさんと行ってくれよ、男同士じゃ面白くないよ~~」
耕助は結局引きずられて行った。劇は面白かったが、この素晴らしいデートのシチュエーションが、ひどく無駄
に終わったようで、勿体ない思いだった。
「面白かったなあ、耕ちゃん」
耕助に引き換え風間は上機嫌だった。
「まあね」
「こうやって昼間遊ぶの久しぶりだなあ」
「まあね…」
――何でこの男はこう嬉しそうなんだ…このプロジェクト、先が思いやられるぜ。
ロビーに出た所で、耕助は不意に風間に袖を引っ張られた。
「あそこの外人と一緒に居る着物の女、分かるか?」
耳元で風間がささやいた。風間の視線の先には、三十前後位の、色白で細身の、水際だった美人が立っていた。でかくて毛むくじゃらの外人と、プログラムを見ながら楽しげにしゃべっている姿は、このロビーでも目立っていた。側を通る人々は皆一様に一瞥をくれていた。
「美人じゃん。新しい金星か?あの外人にゃ勝てないよ」
軽く口笛吹いて耕助はからかうように言った。内心いらいらしていた。
「冗談じゃない。だから君は独り者なんだ」
「人のこと言えるか。自分はもっと始末が悪いくせに」
二人は言い合いながら玄関の方へと歩いていった。女と外人の二人連れの横をすり抜けるとき、風間は苦々しげに、
「あれだよ、篠崎と妙な噂の立っている、古館倭文子というのは…」
とささやいた。さすがに耕助もぎょっとして女を見直した。篠崎とは、ヤミ屋時代からの、風間の友人である。
古館倭文子は元伯爵の古館辰人の夫人であったが、篠崎慎吾が元古館伯爵のものであった名琅荘を手に入れたのがきっかけで、斜陽貴族の辰人夫人である倭文子に篠崎が目を付け、自分の仕事の接待に倭文子を利用するようになったのである。倭文子も自分の能力を活かして働くことに、張り合いを見つけたようで、二人は実に良い関係にあった。そして、実際に男女の仲としても、良い関係にあるのではないかと口さがない人達の間では、話題に上っていたのである。
しかし横をすり抜けるときふっと聞こえた英会話も流暢だったし、表情が活き活きしていて、いかにも才気煥発という感じだったので、なんだか好感が持てて、そんな問題を起こしても応援したくなるような女だった。
ただ、妖しいまでの美しさに、背筋を貫く冷たいものを禁じ得ないのがひっかかったが、
「凄く上等の女じゃないの。何でそんなに嫌なんだ」
「君にゃ言うても分からん。あの女は、良くない」
「だけど本人達が好き合ってたらしょうがないじゃん。回りがどうこう言う問題じゃないだろ?」
「好き合ってたらな…」
風間は歯切れ悪く言うと、片手を上げてタクシーを止めた。側に停まっていたタクシーがすっと寄ってきた。運転手が内からドアを開けると、風間はエスコートするようにドアの取っ手に腕をかけ佇んだ。耕助は動じる風もなく、奥へ乗った。
「ご苦労さん」
とりすまして耕助が言った。
銀座へ出ると、数寄屋橋付近で降りて、あるビルの地下にあるカウンターのみの渋いバーへと二人は入っていった。辺りはもうすっかり暗くなっていた。
「耕ちゃん、もっと飲めよ」
風間が勧めた。耕助は元々いける口ではないので、自分が悪酔いする前に計画を済ませる事にした。今回の計画とは、とある薬――腹痛を起こす、を飲ませて、おせつに看病させ、風間に彼女の大事さを改めて思い知らせる、というまずはオーソドックスな方法。
「金田一さんは、お酒が苦手でしたよね。最近ストロベリーリキュールが手に入ったんですよ。ストロベリーフィズなんか、どうですか?」
顔馴染みのバーテンが声をかけた。
「あ、うん、いいね」
耕助は袂から錠剤を風間の水割りのグラスに放り込みながら相づちを打った。バーテンはシェーカーを振り始めた。
耕助が風間の方を伺っていると、風間は気付かず飲み下した。
「あ、これおいしい」
自分の前に出されたピンクの液体は、甘くておいしかった。耕助は緊張で渇いたのどを、甘い液体で潤した。
「もっと作ったげて」
風間が注文した。
二人はそれからひとしきり世間話をしながら酒を飲み続けた。
風間はしかし待てどくらせど腹痛を起こさない。変だなーと思っている内、耕助の方が酔いつぶれてしまった。
「耕ちゃん!」
カウンターにつっぷした耕助を、風間はゆさぶった。
「あー先生って弱かったんですね。甘く見て飲み過ぎたんだな。結構きくしな、コレ」
バーテンは呑気に頭を掻いた。
風間はツケで慌てて店を出ると、タクシーを止め、乗り込んだ。耕助の肩を抱きながら、ぐったりとした耕助のつらそうな様子を見ると、訳もなく身体中を血が駆け巡るのを感じるのだった。肩を抱く手に、うっすらと冷や汗をかきながら、どこかで休んだ方がいいかも知れない…と風間は思った。
――どこか近くに、ホテルかなんかあったかな…
風間は二人でホテルに入ったときの事を想像して、下半身を硬くした。
無防備に横たわる耕助、それを見下ろす自分…。
――ちょっと待てよ、なんなんだ、そりゃ…
ごくり、と風間の喉が鳴る。しかし彼はもう以前のようには、狼狽しない。彼はもう、ある自覚を持って耕助に相対していたのだった。
――おれは、耕ちゃんが好きだ。それはもう、動かしがたい、事実だ。だけど、それは別
だろう?
去年そのことに気づいてから、何度か口づけたいという欲求を覚えることはあった。その身体を自分の側に、中に抱き留めていたいと思うことはあった。
しかし肉欲は別だ。自分と同じ同性の身体を、どうしたら満足などできるだろう。…
そう自分を偽りながらも、右手で、彼を煽り立て、その乱れる様を見るだけで自分はひどく満足できるのだと、本当は彼は既に気づいていた。
風間は頭を振ると、耕助から腕を外し、窓の外を見た。
松月の外で車の止まる音を聞いて、おちかは玄関へ飛び出した。上手くいったかしらと胸ワクワクで板に立っていると、風間のしっかりした声が
「開けろ」
と怒鳴った。おちかは目を丸くした。
――あっ、あいつ失敗しよったな。
「おちかさん、離れ、床のべて」
おちかが戸を開けると、風間が耕助を支えて入ってきた。
「まぁ、どうしたの?」
音を聞きつけておせつがやってきた。
「調子に乗って飲み過ぎた。どうしよう」
心配そうに風間が言う。おせつが腕を伸ばした。耕助を預けると、風間は靴を脱いで上がった。
「布団しけましたよー」
おちかが離れから駆け戻ってきた。風間は耕助を軽く抱き上げると、離れへと歩いて行った。おせつも思い詰めた表情で付いていく。おちかに洗面器とぬれタオルを頼んで。 おちかはそれでも諦めてなかった。せっかく殿のお渡りがあったのだから、風間とおせつをどうにか進展させたかった。もう耕助を当てにしている場合ではない。おちかは手ぬぐいとアルマイトの洗面器を焦って用意して行った。
他の女中達は、その焦りようにただならぬものを感じた。
おちかは離れの障子を開けた。
二人はキスを交わしていた。
――なんて展開だったらおちかの思うつぼだったのだけど、二人は熱心に耕助に目を落としていた。
「おちかさん、慌ててるのは分かるけど、一声かけるように」
風間は姿勢を変えず、言った。
「すみません、持ってきました」
立ったままおちかは言った。
「有り難う。そこに置いといて。ご苦労さん。もう寝ていいよ。お疲れさま」
風間が腕組みをしたまま振り向いて言った。
「いいえ、あたくしが金田一先生を看ています。ですからどうぞお二人ともお休みになって下さいまし」
おちかは廊下に座り込んで頭を下げた。
「いいえ、おちかさんにそんなことまでさせられないわ。どうぞお休みなさい。あなたも。疲れてるでしょう。お風呂に入って休んでちょうだい」
おせつが言った。それでもおちかは廊下に座っていた。
「君にも迷惑はかけられないよ。耕ちゃんを預かってもらってるだけでも厚かましいのに、どうぞおせつも寝とくれ。おれが一晩中付き添ってるから」
恐縮そうに風間がおせつに言った。そして振り返った。
「とにかくおちかさんにそんな義務はないから、気にせず安心して寝とくれ」
ここはおまえの領分じゃないぞと断固とした口調で風間が言った。目にはおまえは関係ないと言わんばかりの突き放した光があったので、おちかは畏して引き下がることにした。
――この旦那はヤクザだったのだ。怒らせたら後が大変。
「それじゃ、申し訳ありませんが、お先に失礼致します。お休みなさいまし」
深々と礼をして立ち上がると、おちかは退却した。渡り廊下を母屋との接点まで来ると、女中共が群がっていた。おちかはくるりとUターンした。
「おちかさん、どうでした…あれ、何処行くんですか?」
「シーッ、黙っててっ、」
低く静かにたしなめると、おちかは足音殺して離れに逆戻り、熱心に柱に身を寄せ、障子にへばりついている。
「ねえ、おちかさんて…」
「うん」
「もしかして…なのかしら」
その不可解な言動を見守りながら、女中達はいぶかしげにある疑惑を持ち出していた。
――ああ~、いらいらしちゃう。何二人して黙りこくって金田一さん穴の空くほど見つめてんのよっ。金田一さん、失敗もいいとこ、最悪の展開やんけ…!
耕助は苦しそうに荒い息で、ぐったりとぶっ倒れていた。
枕の上座に風間が、その横におせつが。
「いつも世話かけるな」
ポソリと風間が言った。それを聞いておせつははにかんで笑った。
「いいえ。あたし嬉しいんですのよ。金田一さんをあたしなんかに預けてくれて。こんな大事な人を、あたしに預けてくれたって時たまうぬぼれたりして。ただの女より一歩昇格したかしら、なんてね…その分あなた、他の女のとこより寄ってくれるし。金田一さんのついでに、だろうとね」
おせつは白く細い指で、耕助の額の手ぬぐいを絞った。
「おせつ、…おまえだけだよ。わがまま言えるのは。君はただの女じゃないさ。ホントに世話になるね。有り難う」
「いやだわ、今更」
風間はそっとおせつの肩を抱いた。障子の外で覗いていたおちかは、思わずいいぞ、いいぞとぐっと拳を握りしめた。
「そんなことしてる時じゃなくてよ」
耕助が目の前に横たわっているので照れたのか、おせつは風間の腕を外した。
「これからも色々手を焼くことと思う。宜しく頼む」
風間は自分の家族のことのように頭を低く下げた。
「他人のようにおっしゃらないで下さいよ」
――いいぞ、いいぞう。
障子の陰でおちかは興奮していた。雨降って地固まる。
――違う違う、災い転じて福となす。いい展開になってきたやんか。
――もっと、いけいけ、ドーンと行け!
おちかの拳に益々力が入った。
「あの時以来ね」
「えっ?」
「ホラ、前、彼撃たれそうになってショックで寝込んじゃった時があったじゃない。あの時もあなた、熱心に、一晩中看病してた」
「そうだったな…おれのせい、みたいなもんだったからな」
――そう言えば、そんなことがあった。思えばあの時から耕ちゃんが大きく育っていったんだっけ。あの頃は、最も大事でおれの恩人でもある友人だったんだけど、自覚が無かっただけだな。
風間は耕助に視線を落としながら、おせつが邪魔なような、有り難いような気がしていた。
「妬けたのよ」
おせつが溜息をついた。
「あたしが病気になっても、金田一さんほどに心配してくれるかしら」
風間はびっくりしたようにおせつを見ると、すぐに視線を反らした。
「ばかね、あたしって」
「ばか、…するよ」
自嘲気味に言うおせつがいじらしく、つい風間は優しさを出してしまうのだった。肩を抱き寄せ、唇を塞いだ。
おちかはそれを見ると満足して帰ることにした。ホッと嘆息すると、音もなく立ち去った。
おせつはいつの間にか寝てしまっていた。確か外が明るくなって雀が騒ぎ出したのは覚えていたのだけれども…風間がそっと毛布をかけた。
「ん……」
耕助が少し寝返りを打ったので、額の手ぬぐいがすべり落ちた。
風間はそっと拾うと、アルマイトの洗面器に入れて、右手を耕助の頬に触れた。
親指が柔らかな唇をなぞり、彼はそのまま手を喉へすべらせた。微かな圧迫感に、苦しげに耕助の喉が上下した。
風間はその表情を間近で見つめ続けた。その目には、隠しきれない熱い光を湛えながら。